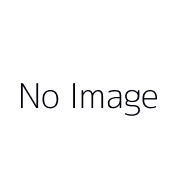樹木の剪定

- 「お隣との境界部分を超えて伸びている枝だけを切りたい」「庭の樹木が伸びてしまい、お隣の家の日照を悪くしている」「隣家に葉っぱが落ちてしまっている」などのきっかけでご依頼を多く頂きます。
庭師さんに頼むほどではない庭木のお手入れから、しっかりしたお庭作りまで、幅広いご希望にお応えすることが可能です。ガーデニングのお手伝いなども含め、お庭全体をコーディネートすることもできます。
木の大きさや枝の伸び具合、場所などによって作業方法も変わるため、事前にお伺いしてご希望をお聞きすることが必須です。
※作業の際に、電気や水道を使用させて頂く場合がございます。
お借り出来ない場合は作業時間が長くなることがありますので、ご了承ください。
※現場環境により、料金が変わる場合があります。
【こちらもオススメ】
ご依頼のきっかけ参考例
- 庭がジャングルみたいになってきちゃって…剪定して形やバランスを整えてきれいにしたいのよ
- 不要な枝を取り除いて、植物や木が元気に育つように見栄えよく維持したいけど、剪定の仕方がよくわからなくて
- 自分でやるのは時間も体力もいるし、後片付けも大変だから、相談しながらやってくれるところはないかしら
- 専用の道具もないし、季節やタイミングをみながら庭木のケアをしてもらえないかな
- 動画でご紹介
- ワンポイント
- ・剪定とは、ある樹木を一定の方式にしたがって整枝するために、枝や小枝を切り取ることを言います。
・整姿とは、乱れたり、込み入った枝葉を矯正して、その樹木本来の特性を出現させる技術です。枝を切るだけでなく、シュロ縄で他方に誘引したり、添え竹をあてがって好みに合った形にします。
・剪定は基本的には頂芽優勢の原理に従い、樹木を剪定する場合は頂部の枝は強く切り、中下部から出ている枝は緩く切ることにより上下のバランスを保ちます。
・年数が経って枝数の多すぎる場合は「枝すかし」をして枝を切る前に間引きする必要があります。
過去の店舗日記から
川崎市中原区で6mの高さの木の選定ならベンリー武蔵小杉店へ2026/02/07

「庭のシンボルツリーが気づけば2階の屋根を超えていた……」
「お隣の敷地まで枝が伸びていて、そろそろ苦情が来そうで怖い」
高さ$6\text{ m}$。これは一般的な住宅の2階の軒先に届く高さです。このクラスの高木の剪定は、単なる「ガーデニング」の域を超え、半分は「高所作業」というプロの領域に足を踏み入れることになります。
自分でやれば数万円の節約になりますが、一歩間違えれば大怪我や、大切な樹木を枯らしてしまうリスクも隣り合わせ。「自分にできるのか、プロに頼むべきか?」の境界線も見極めながら、安全に、そして木を健康に保つための高木剪定・完全マニュアルを詳しく解説します。
樹木の剪定 詳細はこちら