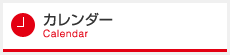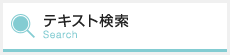川崎市中原区で5ドア冷蔵庫の搬入ならベンリー武蔵小杉店へ
2025/07/08

本日のご依頼です。
冷蔵庫の階段搬入の手順と注意点を以下にまとめます。
5ドア冷蔵庫 マンション2階への階段搬入
1. 事前確認と準備
-
通路の確認:
-
玄関ドア、廊下の幅: 冷蔵庫が通るか? ドアの蝶番を外す必要があるか?
-
階段の幅と踊り場の広さ: 冷蔵庫を立てたまま通れるか? 途中で向きを変えるスペースがあるか?
-
天井の高さ: 冷蔵庫を傾けた際に天井にぶつからないか?
-
手すりや障害物: 階段の手すりが邪魔にならないか? 外せるものか?
-
最終的な設置場所までの通路: キッチンへの入口など、最終的な搬入経路も確認。
-
採寸の徹底: 冷蔵庫の寸法(高さ、幅、奥行き)を正確に測り、搬入経路の各所の有効寸法と比較します。特に奥行きを測り忘れると、階段の踊り場で回転できないケースが多いです。
-
人員の確保:
-
道具の準備:
-
毛布、段ボール、養生マット: 搬入経路の床、壁、階段の段差などを保護します。冷蔵庫本体の保護にも使います。
-
台車(階段運搬用): 専用の階段昇降台車があれば非常に安全性が高まります。しかし、高価なので個人で用意するのは難しいかもしれません。
-
固定ベルト、ロープ: 冷蔵庫を固定し、滑り落ちないようにします。
-
軍手、滑り止め手袋: グリップ力を高め、怪我を防ぎます。
-
ヘルメット、安全靴: 万が一の落下に備えます。
-
ラチェットレンチ、ドライバー: ドアや手すりなど、必要に応じて外すための工具。
-
当て木、ジャッキ(補助的に): 傾斜で一時的に支える必要がある場合。
-
冷蔵庫の準備:
-
電源を切る: 最低でも搬入の数時間前には電源を切り、庫内の霜取りと水抜きを済ませておきます。
-
中の物を全て出す: 棚板や野菜室、製氷皿なども全て取り出します。扉が開かないようにテープで固定します。
-
コンセントコードの固定: コードが邪魔にならないようにまとめて固定します。
2. 搬入作業の手順
-
養生: 搬入経路となる玄関、廊下、階段、壁、床などを徹底的に養生します。特に角や曲がり角、ドア枠などは入念に行います。
-
冷蔵庫の傾け方:
-
基本的には、**冷蔵庫を立てた状態(正面が上)**で運ぶのが理想です。しかし、天井の高さや階段の傾斜によっては、ある程度傾ける必要があります。
-
最近の冷蔵庫は耐震性を考慮して設計されていますが、あまりに大きく傾けすぎると、コンプレッサー内のオイルが液だれを起こし、故障の原因になることがあります。メーカーによっては、傾けてもよい角度が指定されている場合がありますので、事前に確認してください。 一般的には45度以内と言われることが多いですが、確実ではありません。
-
階段の昇降:
-
下で支える人(基本2名): 冷蔵庫の下部を持ち、段差を乗り越えながら押し上げます。重心を意識し、バランスを崩さないようにします。
-
上で引き上げる人(基本1名): 冷蔵庫の上部を持ち、引き上げます。滑り落ちないようにしっかりと固定ベルトなどを使い、慎重に力を入れます。
-
声掛けと連携: 「せーの!」「よし!」「ストップ!」など、常に声を掛け合い、息を合わせることが非常に重要です。
-
重心のコントロール: 重い方を下にして運ぶのが基本ですが、階段では常に重心が移動します。傾斜に合わせて、常に安定する位置を探しながら運びます。
-
踊り場での回転: 最も難しいポイントの一つです。十分なスペースがあれば立てたまま回転できますが、狭い場合は大きく傾けたり、一旦地面に置いて向きを変える必要があります。この際、壁や手すりにぶつけないよう細心の注意が必要です。
-
設置場所への移動:
-
電源投入:
以上です。
ご依頼頂き、ありがとうございました。
東京都世田谷区で粗大ごみ出し代行なら、ベンリー武蔵小杉店へ
2025/07/07

本日のご依頼です。
東京都世田谷区でマンションの階段から、解体が必要な本棚の粗大ゴミ出しをする場合の手順と注意点について説明します。
世田谷区の粗大ごみの基本ルール
まず、世田谷区では粗大ごみの定義が「一辺の長さが30センチメートルを超えるもの」です。本棚の場合、多くはこれに該当します。重要なのは、**「解体しても原則として解体前の大きさで料金が決まる」**という点です。つまり、小さく分解しても可燃ごみや不燃ごみとしては出せず、粗大ごみとして処理する必要があります。
参考:世田谷区 粗大ごみの処理手数料について https://www.city.setagaya.lg.jp/02239/382.html
1. 世田谷区の粗大ごみ収集に申し込み、運び出しを行う場合
世田谷区では、粗大ごみは原則として「指定された場所(通常は自宅前)」まで自分で運び出す必要があります。そのため、今回、粗大ごみ運び出し代行のご依頼を頂きました。
手順:
-
世田谷区粗大ごみ受付センターに連絡し、本棚の収集を申し込む。
-
電話: 03-5715-1133 (月曜日~土曜日の午前8時~午後9時、祝日可・年末年始除く)
-
インターネット: 世田谷区粗大ごみ受付センターのウェブサイト https://www.sodai-setagaya.jp/eco/view/setagaya/top.html
-
チャットボット: 区のホームページの右下に表示されるもの
-
本棚のサイズを測っておく: 縦・横・奥行きの最長辺とその次に長い辺を控えておくとスムーズです。
手数料の確認と粗大ごみ処理券の購入:
-
申し込み時に本棚の収集手数料が案内されます(本棚は400円〜2,300円の範囲が多いようです。解体前の大きさで判断されます)。
-
コンビニエンスストアなどで、手数料分の「有料粗大ごみ処理券(A券200円、B券300円)」を購入します。
-
本棚の解体
-
粗大ごみ処理券の貼付と排出:
-
購入した粗大ごみ処理券に「受付番号または氏名」と「収集予定日」を記入し、解体後の各部材の見やすい位置に貼り付けます。
-
収集日の朝8時までに、指定された場所(通常はマンションのエントランス付近など、収集車がアクセスしやすい場所)へ運び出します。
-
階段からの運び出し: 解体しても重い部材がある場合は、複数人での作業が必要になることがあります。通路を傷つけないように、毛布や養生シートなどで保護します。
以上です。
ご依頼頂き、ありがとうございました。
川崎市中原区で複合機の搬出入ならベンリー武蔵小杉店へ
2025/07/06

本日のご依頼です。
2拠点の複合機の入れ替え、移動元がマンション、移動先が雑居ビルでエレベーターあり、軽トラックでの運搬、移動距離30分程度、4段程度の段差を人力で持ち上げる作業でした。
複合機入れ替え手順
複合機の入れ替え作業は、精密機械の運搬と設置、そしてネットワーク設定が伴うため、慎重な計画と実行が必要です。以下に手順をまとめました。
1. 事前準備と確認
-
複合機のサイズと重量確認: 入れ替える複合機それぞれの正確なサイズ(幅、奥行き、高さ)と重量を確認します。搬入・搬出経路の確保に不可欠です。
-
搬入・搬出経路の確認:
-
必要な工具と資材の準備:
-
運搬用具: 台車(重量に耐えられるもの)、毛布やエアキャップなどの緩衝材、ロープや固定ベルト、軍手。
-
養生資材: 経路の床や壁を保護するための養生シート、養生テープ。
-
その他: ドライバー(必要に応じて)、清掃用具(設置場所の清掃用)。
-
軽トラックの準備: 複合機が安全に積載できるか確認し、荷台の固定具などを準備します。
-
人員の確保: 複合機の重量によっては、複数人での作業が必要になります。特に4段の段差での持ち上げ作業は、3名で行いました。
-
日程調整と連絡: 入れ替え作業の日程を決定し、両拠点の関係者(管理者、担当者など)に事前に連絡し、エレベーターの使用許可や駐車スペースの確保などを行います。
-
データのバックアップ: 必要であれば、複合機内の設定やアドレス帳などのデータを事前にバックアップしておきましょう。
2. 移動元での作業(マンション)
-
最終確認: 複合機の電源が落ちていることを確認し、ケーブル類を全て取り外します。トナーや用紙などの消耗品が外せる場合は外しておくと、運搬中の破損リスクを減らせます。
-
養生: 複合機を搬出する経路(玄関からエレベーター、特に段差周辺)を養生シートで保護します。
-
複合機の移動:
-
軽トラックへの積載:
3. 輸送
4. 移動先での作業(雑居ビル)
-
搬入経路の養生: 軽トラックから複合機設置場所までの経路を養生シートで保護します。特に、エレベーターや廊下、ドア周りなど、複合機が通過する場所を念入りに養生します。
-
複合機の搬入:
-
古い複合機の搬出:
-
複合機の設置:
-
動作確認と設定:
5. 後片付け
-
安全第一: 重量物の運搬には常に危険が伴います。無理な作業はせず、安全を最優先にしてください。必要であれば、作業を中断し、休憩を取ることも大切です。
-
二人以上での作業: 特に段差での持ち上げや、複合機の積載・降ろし作業は、複数人で行うようにしてください。
-
静電気対策: 複合機は精密機械のため、静電気による故障のリスクがあります。特に冬場は注意し、触れる前に金属に触れるなどして放電することをおすすめします。
この手順が、複合機の入れ替え作業をスムーズに進める一助となれば幸いです。
ご依頼ありがとうございました。
川崎市中原区で引越のお手伝いならベンリー武蔵小杉店へ
2025/07/05

本日のご依頼です。
お母様と娘さんお二人での軽トラックを使った引越し、大きな家具の運搬は大変な作業ですが、計画的に進めれば可能です。引越し元・先ともにエレベーターがあったので、スムーズに進める事ができました。
具体的なやり方と注意点をご説明します。
1. 事前準備(引越し1週間〜前日)
-
荷物量の把握と仕分け:
-
梱包資材の準備:
-
毛布、キルティングパッド、厚手のダンボール: 家具の養生用。複数枚用意しましょう。
-
ガムテープ、養生テープ: ダンボールの封や家具の扉固定に。
-
ロープ、ラッシングベルト: 軽トラックの荷台で荷物を固定するために必須です。数本用意。
-
軍手(滑り止め付きがおすすめ): 荷物の運搬時に必須。人数分。
-
台車: エレベーターや部屋での移動に非常に役立ちます。折りたたみ式でも頑丈なものが良いでしょう。
-
カッターナイフ、ハサミ: 開梱や梱包作業に。
-
ドライバー、六角レンチなど工具: 家具の分解・組み立てが必要な場合。
-
ゴミ袋: 引越し元で出たゴミをまとめるため。
-
家具の事前準備:
-
冷蔵庫: 前日までに中身を空にし、霜取り・水抜きをしておく。庫内の棚やトレーは外して別に梱包するか、動かないようにテープで固定する。扉は開かないようにテープでしっかり固定。運搬後、数時間〜半日程度置いてから電源を入れる(コンプレッサー内のオイルが安定するため)。
-
洗濯機: 水抜きをする(取扱説明書参照)。給水・排水ホースを外し、内部のドラムが動かないように固定ボルトを取り付ける(輸送ボルト)。
-
ベッド: 可能であれば分解する。ネジなどの部品はなくさないように袋に入れ、ベッドフレームにテープで貼り付けておく。
-
タンス、棚: 中身を全て出し、空にする。扉や引き出しは開かないようにガムテープや養生テープでしっかりと固定する。分解できるものは分解する。
-
ソファ: 大きなビニール袋などで包み、汚れや傷を防ぐ。
-
テレビ、PCなどの精密機器: 元箱があれば元箱に入れる。なければ緩衝材(プチプチなど)で厳重に包み、厚手のダンボールに入れる。
-
マンション管理会社への連絡:
2. 引越し当日の作業
引越し元での作業
-
養生:
-
小物類の搬出(先に済ませる):
-
大型家具の搬出:
-
二人での連携: 「せーの」「よし!」など、声をかけ合って息を合わせる。無理な体勢で持ち上げない。腰を痛めないよう、膝を使って持ち上げる。
-
毛布や養生: 運ぶ家具は毛布やキルティングパッドで包み、傷や汚れを防ぎます。特に角は重点的に。
-
台車の活用: 部屋の中やエレベーター内、エントランスからトラックまでの移動で積極的に台車を使います。
-
エレベーターでの注意:
-
軽トラックへの積み込み:
-
慎重に積み込む: 荷台に毛布などを敷いて、家具の傷つきを防ぐ。
-
立てて積む: 冷蔵庫やタンスなどは基本的に立てて運び、立てて積みます。倒れないように隙間を埋めたり、ロープで固定したりします。
-
隙間を埋める: 布団やクッション、余ったダンボールなどで荷物と荷物の隙間、荷物と荷台の隙間を埋めます。これにより、走行中の荷崩れを防ぎます。
-
ロープやラッシングベルトでの固定(最重要!):
-
軽トラックの荷台にはロープをかけるフック(アオリの内側や鳥居と呼ばれる運転席側の柵)があります。
-
荷物全体を、複数の方向(前方向、横方向、上方向)からロープやラッシングベルトでしっかりと固定します。
-
**「南京結び」や「輸送結び」**など、緩みにくい結び方を覚えておくと便利です(動画サイトなどで確認できます)。
-
走行中に荷物が動かないか、グラグラしないか、実際に揺らして確認しましょう。
-
荷台のアオリ(側面の高さ)を超えるような高さに積む場合は、特に慎重に固定し、道路交通法上、全長の10分の1までの荷物のはみ出ししか認められていない点に注意が必要です。必要であれば赤旗を付けるなどの対応も検討しましょう。
引越し先での作業
-
養生: 引越し元と同様に、搬入経路の養生を行います。
-
荷降ろしと搬入: 軽トラックから荷物を降ろし、エレベーターを使って新居へ運び込みます。
-
家具の組み立て・設置: 必要に応じて家具を組み立て、所定の場所に設置します。
-
最終確認:
3. その他、大切なこと
-
休憩と水分補給: 特に夏場は熱中症に注意し、こまめに休憩と水分補給をとりましょう。
-
無理は禁物: 重い荷物は無理に持たず、台車を使う、二人で協力するなど、安全第一で作業を進めましょう。腰を痛めたり、荷物を破損させたりしないように注意。
-
雨天対策: 雨の予報がある場合は、荷物用の大きなビニールシートやブルーシートを用意し、軽トラックの荷台全体を覆えるようにしておきましょう。家具も防水対策をしておくと安心です。
以上です。
ご依頼ありがとうございました。
川崎市中原区で店舗のフロアタイル貼り替えならベンリー武蔵小杉店へ
2025/07/04

本日のご依頼です。
フロアタイル貼り替えの一般的な手順とポイントを詳しく解説します。
店舗のフロアタイル貼り替え手順
1. 事前準備
-
現状確認と計画:
-
現在の床の状態を確認します。既存の床材の種類(フロアタイル、Pタイル、クッションフロアなど)、下地の状態(平坦性、乾燥状態、汚れ、ひび割れなど)をチェックします。
-
貼り替えるフロアタイルの種類、色、デザインを決めます。店舗の用途や雰囲気に合わせて選びましょう。
-
必要なフロアタイルの枚数を計算します。予備として数枚多めに用意することをおすすめします(カットミスや将来的な補修用)。
-
重要: 施工前にフロアタイルを室内に搬入し、24時間以上室温に慣らしておきます(温度変化による伸縮を防ぐため)。室温は17~25℃が理想です。
-
道具の準備:
-
作業環境の確保:
2. 既存床材の撤去と下地処理
-
既存フロアタイルの剥がし方:
-
スクレーパーやバールを使い、端から剥がしていきます。固着している場合は、少しずつ力を入れて剥がします。
-
接着剤の種類によっては、水を使って剥がせるソフトタイプと、専用の溶剤が必要なハードタイプがあります。
-
剥がした後の床に残った接着剤は、スクレーパーなどでしっかり取り除きます。必要であれば、専用の溶剤やサンドペーパーで除去します。
-
下地処理:
3. 墨出し(基準線を引く)
4. 接着剤の塗布
5. フロアタイルの貼り付け
6. 端部のカットと仕上げ
-
壁際のカット: 壁際など、フロアタイルがそのままでは入らない部分は、寸法を測ってカットします。
-
カットする際は、フロアタイルカッター(または大型カッターナイフと定規)を使用します。表面にしっかりと切れ目を入れ、パキッと折るようにすると比較的きれいにカットできます。
-
コツ: 壁との間に1mm程度の隙間を空けて貼ることで、温度変化によるタイルの膨張・収縮に対応できます。厚紙などをスペーサー代わりに挟むと良いでしょう。
-
カットした切り口は壁側に向くように配置すると、仕上がりがきれいです。
-
複雑な形状のカット: 柱や配管など、複雑な形状の部分は、型取りをして丁寧にカットします。
-
目地棒(必要に応じて): タイルの隙間をよりリアルな目地のように見せたい場合や、異なるフロアタイルの貼り分けをする場合は、目地棒を挟んで施工します。
-
最終圧着: 全てのフロアタイルを貼り終えたら、再度全体を圧着ローラーでしっかり圧着します。
-
接着剤の拭き取り: タイルの表面にはみ出た接着剤は、乾く前にきれいに拭き取ります。
-
コーキング: 壁際の隙間などが気になる場合は、コーキング材で埋めるとよりきれいに仕上がります。
7. 養生と乾燥
8. 残材の処分
注意点・ポイント
以上です。
ご依頼ありがとうございました。


東京都大田区でカーポートの雨どい清掃ならベンリー武蔵小杉店へ
2025/07/03

本日のご依頼です。
カーポートの雨樋清掃は、詰まりを防ぎ、カーポートを長持ちさせるために大切な作業です。作業の注意点について解説します。
カーポートの雨樋清掃のやり方
1. 掃除の頻度
理想的には年に1~2回が推奨されています。特に、落葉の多い秋の終わりや、花びらや花粉が舞う春の終わりに清掃すると良いでしょう。台風や大雨の後も、異物が詰まっていないか確認することをおすすめします。
2. 準備するもの
-
脚立またははしご: 高い場所での作業になるため、安定したものを準備してください。
-
軍手またはゴム手袋: 詰まった落ち葉や泥は衛生的ではありませんし、怪我の防止にもなります。
-
ゴミ袋: 掻き出したゴミを入れるために使用します。水が抜ける土のう袋も便利です。
-
トングや割り箸、ハンドスコップ: 落ち葉や泥を掴んだり掻き出したりするのに使います。
-
ホース: 詰まりを流したり、雨樋の中を洗い流したりするのに使います。長いもの(20m以上推奨)が便利です。
-
ブラシ(小さめ、柔らかめ): 雨樋の溝や細かい部分の汚れを落とすのに使います。
-
パイプクリーナー(ワイヤー式など): 縦樋の奥の方で詰まりがある場合に有効です。
-
バケツ: 水を入れたり、洗剤を薄めたりするのに使います。
3. 清掃手順
カーポートの雨樋は、大きく分けて横樋(軒樋)と縦樋があります。
3-1. 横樋(軒樋)の清掃
-
安全確保:
-
大まかなゴミの除去:
-
水で洗い流す:
3-2. 縦樋の清掃
縦樋はカーポートの柱に沿って設置されている部分です。
-
ドレンエルボ(ゴミ出しエルボ)の確認:
-
詰まりの除去:
-
外したキャップ内部や、縦樋の入り口に溜まったゴミを取り除きます。
-
縦樋の奥の方で詰まっている場合は、パイプクリーナー(ワイヤー式)を挿入し、詰まりを掻き出します。ワ
-
縦樋の側面を軽く叩いて、詰まっているゴミを下に落とす方法も有効です。
-
水で確認:
4. カーポート屋根の清掃(オプション)
雨樋を掃除するついでに、カーポートの屋根も掃除すると全体がきれいになります。
-
屋根のホコリや汚れを水で洗い流します。
-
頑固な汚れは、柔らかいスポンジやモップ、中性洗剤を薄めた液で優しく擦り洗いします。
-
ポリカーボネート製の屋根は傷つきやすいので、硬いブラシは使用しない様にします。
-
高圧洗浄機を使用する場合は、水圧で屋根材を傷つけないよう注意し、噴射の反動でバランスを崩さないように気をつけましょう。
注意点
-
高所作業の危険性: カーポートの雨樋掃除は高所作業を伴うため、転落などの危険が大きいです。無理な体勢での作業や、不安定な脚立・はしごの使用は絶対に避けます。
-
二人以上での作業: 一人で作業すると、万が一の際に危険です。必ず二人以上で作業し、お互いに安全を確認しながら進めます。
-
破損に注意: 雨樋は比較的デリケートな素材でできていることが多いです。無理に力を加えたり、硬いブラシで強く擦ったりすると破損の原因になります。
-
洗剤の使用: 屋根や雨樋の素材によっては、使用できない洗剤があります。中性洗剤を使用するのが一般的ですが、念のため素材を確認し、目立たない場所で試してから使用します。
以上です。
ご依頼頂き、ありがとうございました。
東京都大田区で蛍光灯の交換ならベンリー武蔵小杉店へ
2025/07/02

本日のご依頼です。
本日のご依頼は、東京都大田区で蛍光灯の交換です。
台所の蛍光灯が急に切れて、その時点で、ご自宅にご高齢の方とお子さんしかいないので、
交換してほしいとご依頼を頂きました。
台所の蛍光灯交換は、タイプによって方法が異なります。まずは台所の蛍光灯がどのタイプか確認します。
1. 蛍光灯の種類を確認する
台所でよく使われる蛍光灯には、主に以下の種類があります。
-
直管型蛍光灯: 細長い棒状の蛍光灯。キッチンでよく見かけるタイプです。
-
グロースタータ形 (FLで始まる型番): 点灯管(グローランプ)という小さな部品が別途ついているタイプ。スイッチを入れてから「チカチカ」と点滅して点灯するのが特徴です。
-
ラピッドスタート形 (FLRで始まる型番): グローランプがなく、スイッチを入れるとすぐに点灯するタイプです。
-
インバーター形 (FHFで始まる型番): グローランプがなく、より効率的に点灯するタイプです。スイッチを入れるとすぐに点灯し、チラつきが少ないのが特徴です。
-
丸形蛍光灯 (FCLで始まる型番): 丸いドーナツ状の蛍光灯。
-
LED一体型照明: 蛍光灯ではなく、LEDチップが組み込まれた照明器具全体を交換するタイプ。
2. 交換前の準備と注意点
蛍光灯交換の際は、以下の点に注意してください。
-
必ず電源を切る: 感電の危険があるため、必ず照明のスイッチを切り、可能であればブレーカーも落としましょう。
-
軍手や手袋を着用する: 蛍光灯はガラス製なので、破片で手を切らないように軍手やゴム手袋を着用しましょう。
-
安定した足場を確保する: 脚立などを使用する場合、ぐらつかない安定したものを使いましょう。
-
新しい蛍光灯を用意する: 現在使用している蛍光灯の型番(FL〇〇、FCL〇〇など)を確認し、同じワット数、同じ形状のものを購入しましょう。型番は蛍光灯の本体に記載されています。光色(昼光色、昼白色、電球色など)も確認しておくと良いでしょう。
3. タイプ別の交換方法
直管型蛍光灯の交換方法
-
照明カバーを外す: 器具についているカバーを外します。多くの場合、ツメを内側に押したり、ネジを緩めたりすることで外れます。取扱説明書があれば確認しましょう。
-
古い蛍光灯を外す:
-
点灯管(グローランプ)を交換する(グロースタータ形の場合のみ):
-
新しい蛍光灯を取り付ける:
-
照明カバーを取り付ける: 取り外した時と逆の手順でカバーを取り付けます。
-
点灯確認: スイッチを入れて、正常に点灯するか確認します。
丸形蛍光灯の交換方法
-
照明カバーを外す: 直管型と同様に、カバーを外します。
-
コネクタを外す: 丸形蛍光灯は、本体から出ている複数のピンが器具のソケットに接続されています。このコネクタをゆっくり引き抜いて外します。
-
古い蛍光灯を外す: 器具に固定されているクリップやフックを解除して、蛍光灯を取り外します。
-
新しい蛍光灯を取り付ける:
-
照明カバーを取り付ける: カバーを元に戻します。
-
点灯確認: スイッチを入れて、正常に点灯するか確認します。
蛍光灯からLED照明への交換について
近年、省エネや長寿命の観点から、蛍光灯からLED照明への交換を検討される方が増えています。
今回は実施しませんでしたが、LED照明への交換方法も記載致します。
-
蛍光灯型LEDランプに交換する場合:
-
照明器具ごとLED一体型に交換する場合:
蛍光灯が点滅したり、スイッチを入れてもすぐにつかなかったりする場合は、蛍光灯だけでなく、点灯管(グローランプ)や照明器具本体の寿命が近づいている可能性もあります。特に10年以上使用している照明器具は、器具自体の交換も検討されることをおすすめします。
以上です。
ご依頼頂き、ありがとうございました。
川崎市中原区で跳ね上げ式ダブルベッドの部屋をまたぐ移動ならベンリー武蔵小杉店
2025/07/01

本日のご依頼です。
本日のご依頼は跳ね上げ式ベッドの移動です。
跳ね上げ式ダブルベッドを部屋をまたいで移動させる一般的な方法
1. 分解して移動し、再組み立てする
これが最も安全で現実的な方法です。跳ね上げ式ベッドは、収納部分とフレーム、そして床板(マットレスを載せる部分)から構成されており、これらを分解することが可能です。
準備:
-
取扱説明書: 最も重要です。分解・組み立て手順が載っています。
-
工具: ドライバー(プラス・マイナス)、六角レンチ、スパナ、軍手など。
-
梱包材: 毛布、バスタオル、エアキャップ(プチプチ)、段ボールなど。傷防止用。
-
養生テープやマスキングテープ: 部品をまとめる、どこから外したかメモする用。
-
筆記用具: メモを取る用。
-
収納ケースや袋: 小さなネジや部品をなくさないため。
手順:
-
マットレスの取り外し:
-
収納物の取り出し:
-
跳ね上げ機構の固定・解除:
-
フレームの分解:
-
部品の搬出・搬入:
-
再組み立て:
-
マットレスの設置・最終確認:
移動前に確認すべきこと
-
移動先のドアの幅と高さ: ベッドの最大寸法(特にヘッドボード、フットボードの高さ、フレームの幅)が通るか計測。
-
通路の広さとカーブ: L字型などの曲がり角があるか、十分なスペースがあるか。
-
障害物: 廊下の突き出た部分、柱、段差など。
-
ベッドの構造: どのようなタイプか(メーカーやモデルが分かれば、ネットで取扱説明書を探せることがあります)。
以上です。
ご依頼頂き、ありがとうございました。